「不動産クラウドファンディングは途中解約できないのがデメリット」
「途中解約できる不動産クラウドファンディングはあるの?」
といった疑問を抱えている方もいるでしょう。
不動産クラウドファンディングは、1万円から投資できるのが魅力の不動産投資です。
しかし、まとまった配当を受け取るには、数十万~100万以上の金額を投資する方もいます。
その一方で、長い場合は12カ月を超える運用期間があるファンドに投資した場合、途中解約したい事情が発生することもあるでしょう。
今回は、途中で解約できる不動産クラウドファンディングを9社紹介します。
☆CREALが当サイトと限定アマギフキャンペーン!☆
上場企業運営で、実績トップクラスの「CREAL」が注目を集めています。
そんなCREALが、当サイト限定タイアップキャンペーンを実施中です!
新規投資家登録だけで、Amazonギフト券2,000円分、投資額に応じて最大48,000円分のAmazonギフト券がもらえます。
公式サイトではキャンペーンは実施していないため、注意してくださいね。
豪華なキャンペーンが実施されているこの機会に無料の投資家登録をしてみてはいかがでしょうか。
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング9選
不動産クラウドファンディングには、中途解約や譲渡できるサービスもあります。
中途解約、譲渡ができないサービスにはその旨が必ず記されているので、確認しましょう。
ここでは、中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディングを9社を紹介します。
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング1. COZUCHI
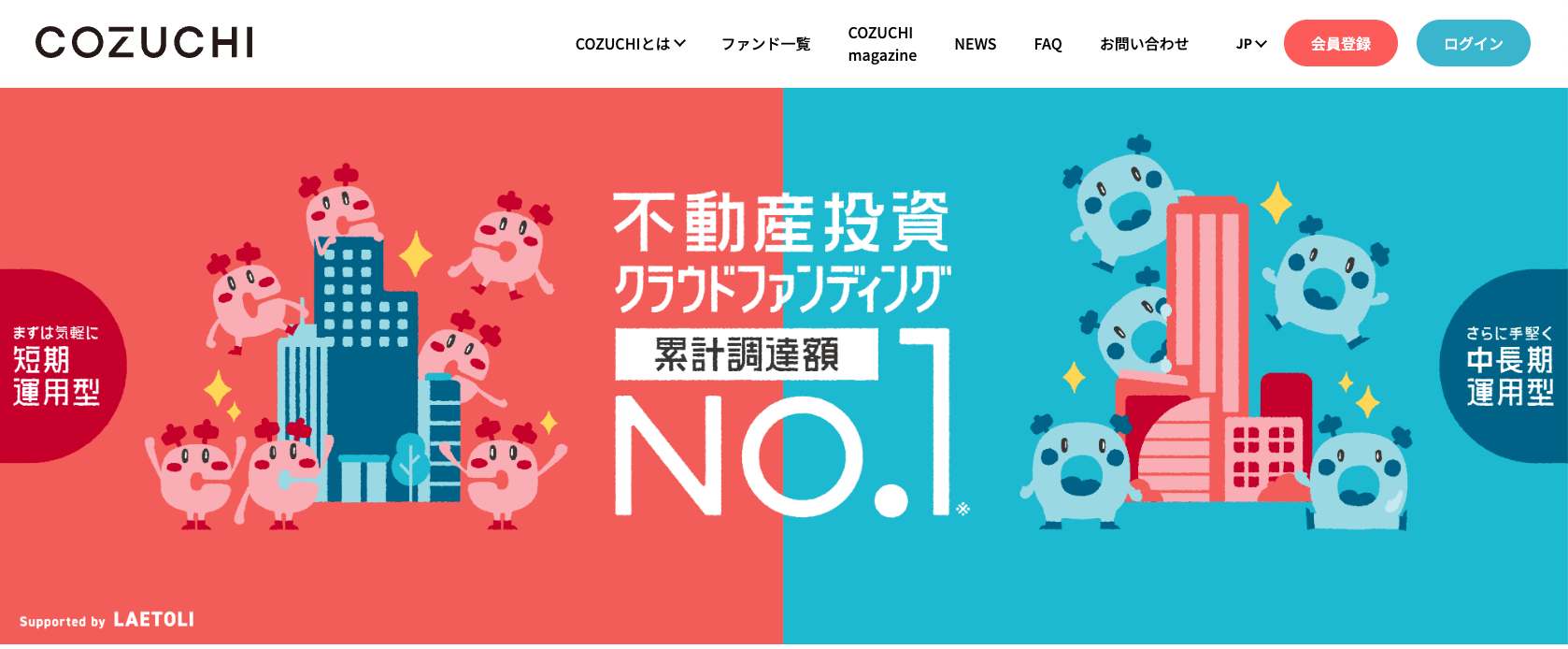
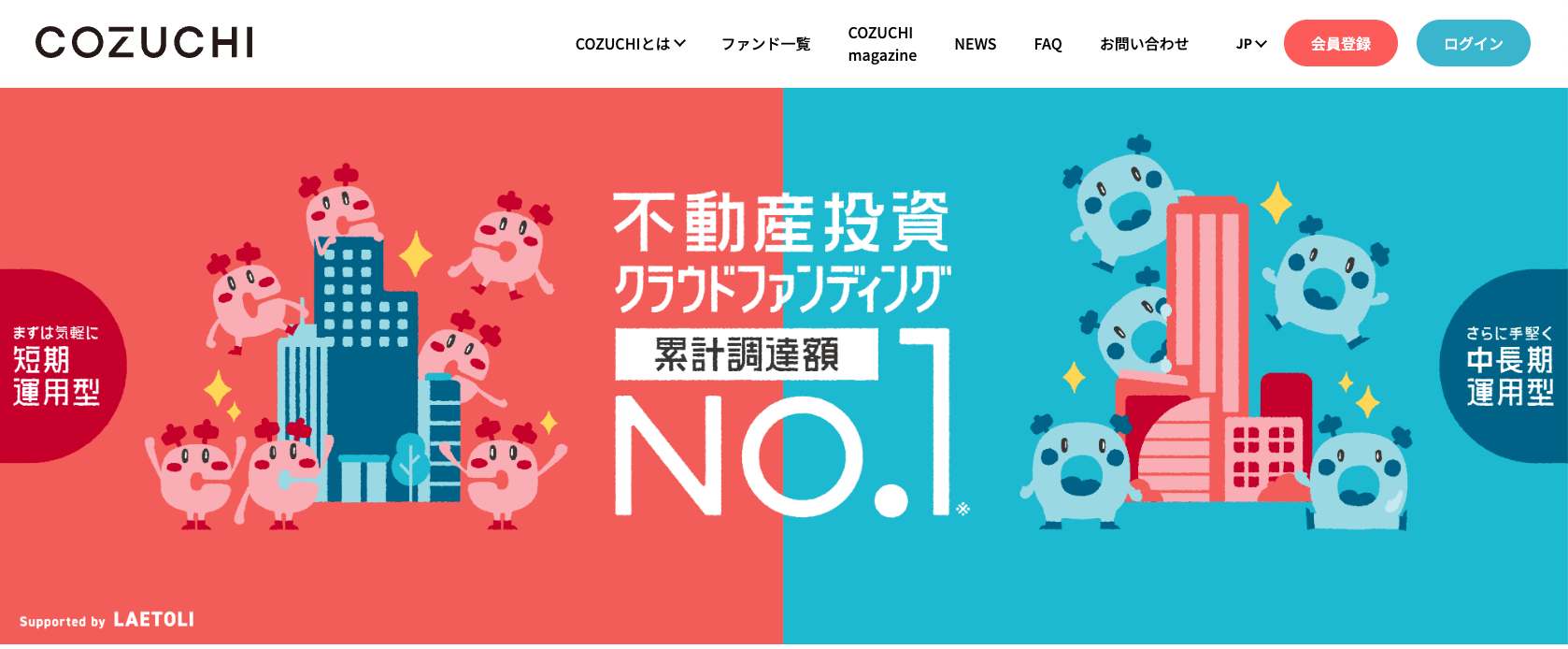
COZUCHIは、初心者から不動産投資のプロまで幅広い投資家に対応している不動産クラウドファンディングサービスです。
短期運用ファンドと中長期運用型ファンドの2種類のファンドで展開しているのが特徴です。
COZUCHIでは、購入後にマイページから買い取りの申し込みを行えば、いつでも途中解約できます。
ただし、短期運用型ファンドでは途中解約時に手数料(投資元本の3.3%)が発生します。
一方、中長期運用型ファンドでは手数料なしで途中解約が可能です。
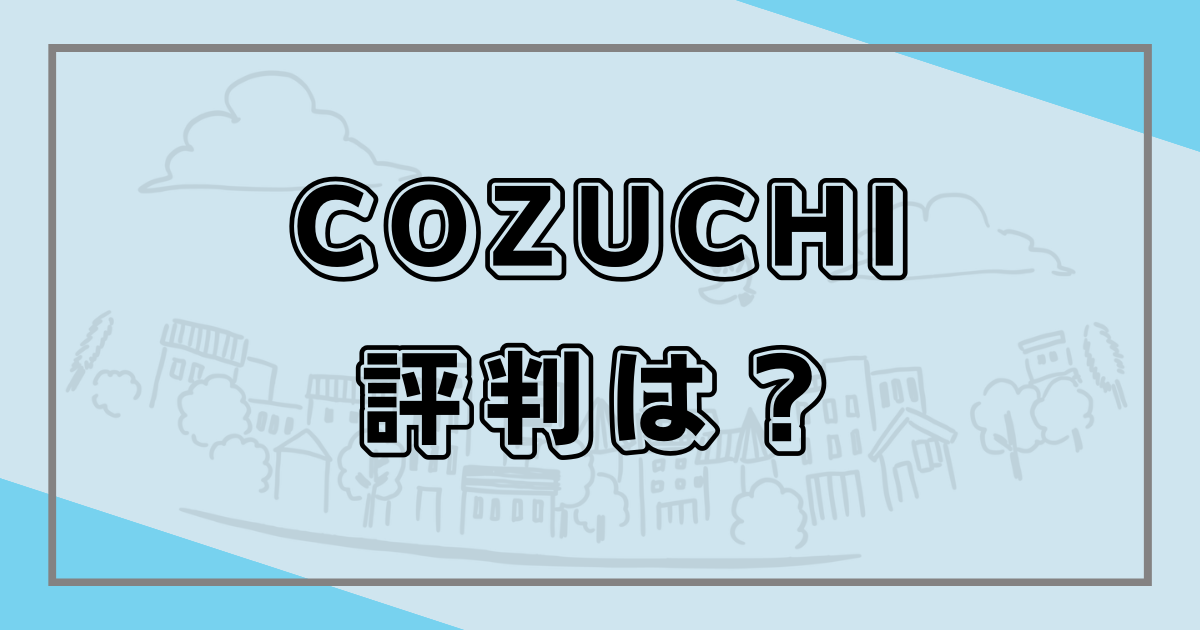
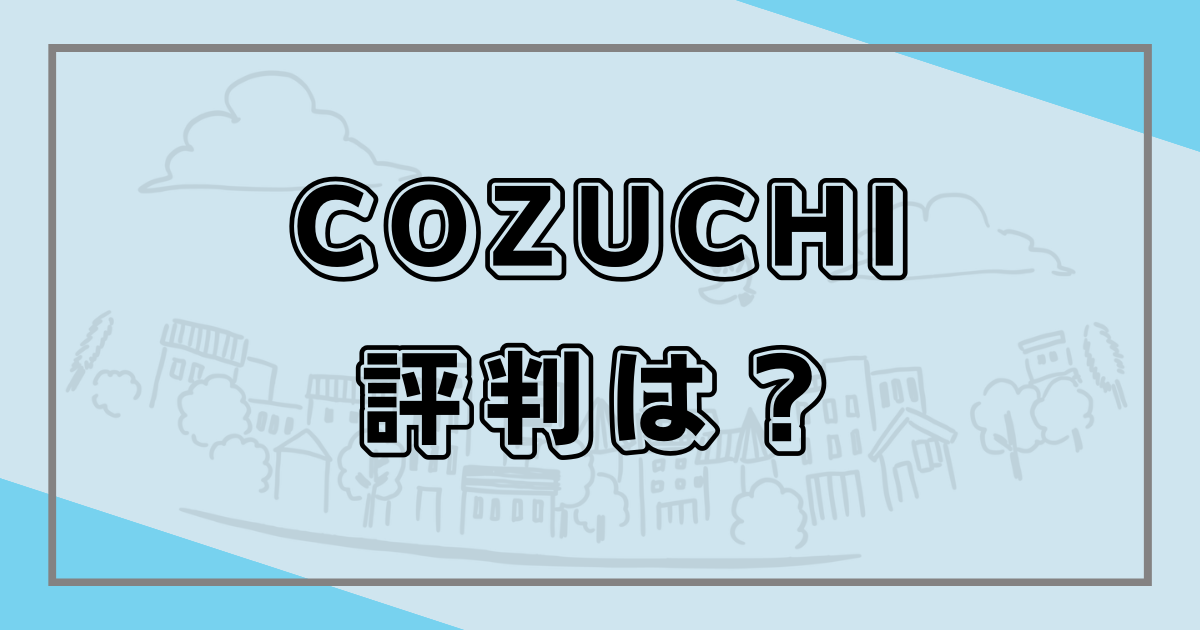
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング2. GOLDCROWD(ゴールドクラウド)
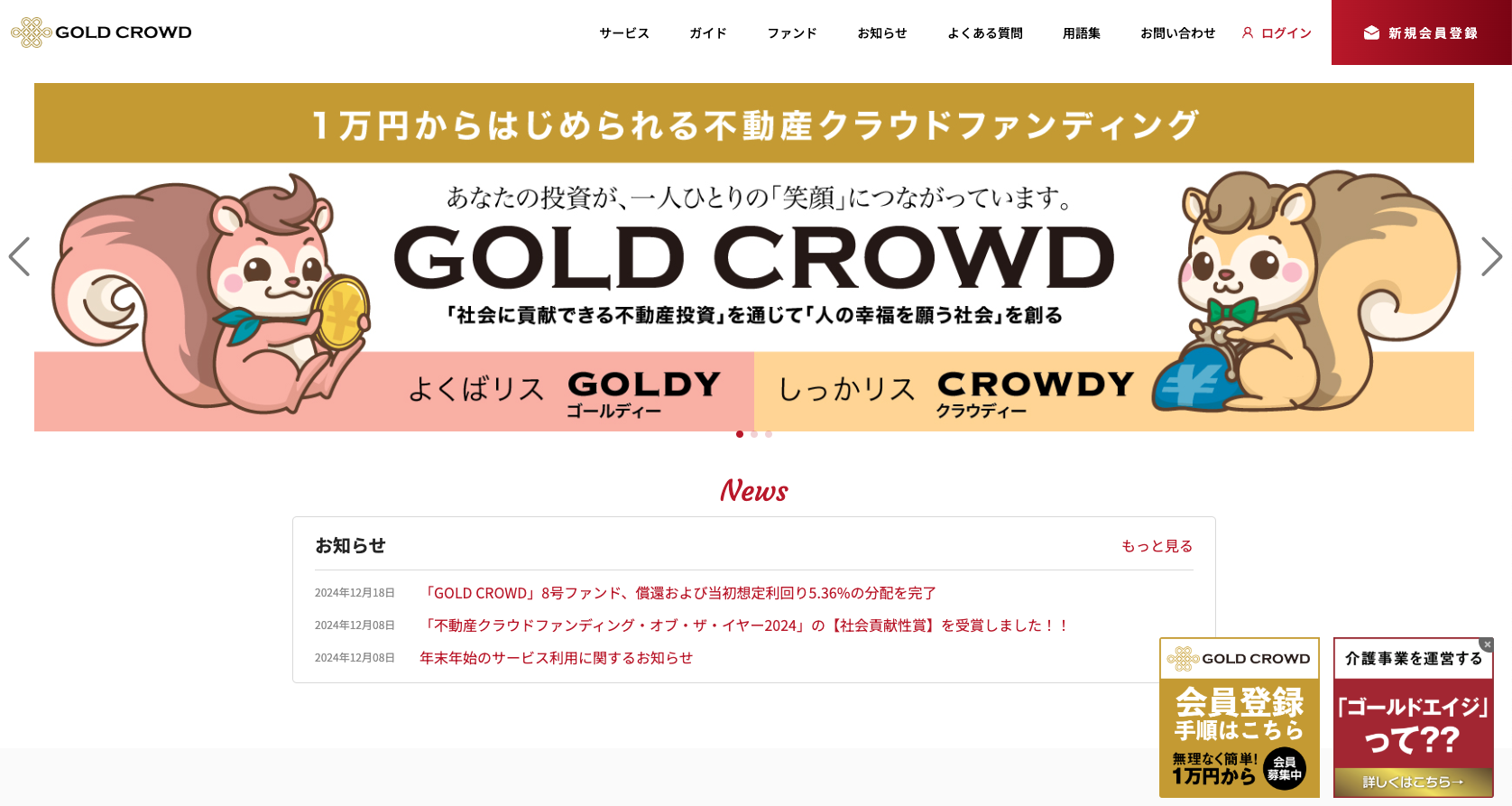
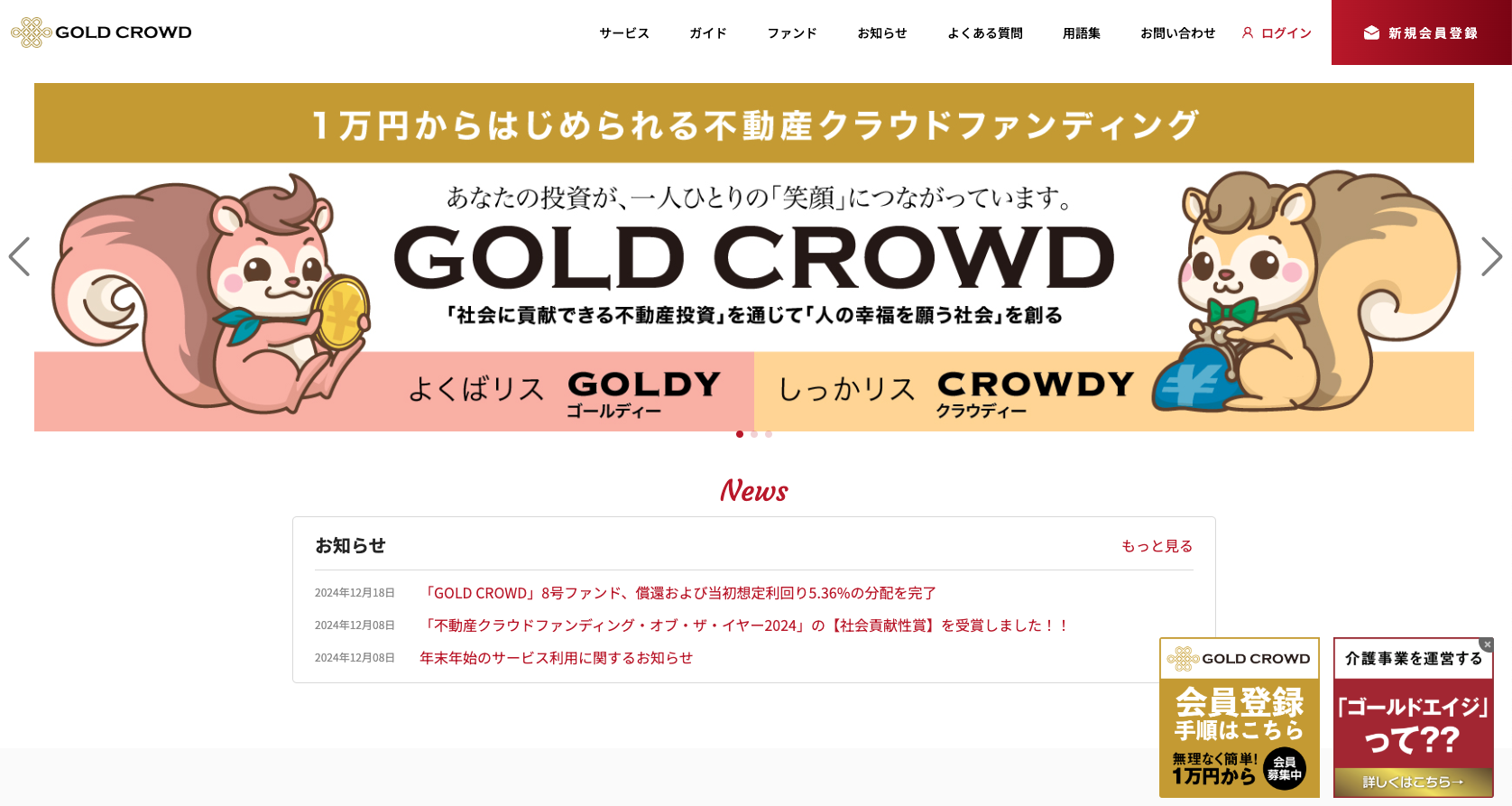
GOLDCROWDは、原則として解約はできませんが譲渡は可能です。
譲渡する場合は、譲渡には事務手数料10,000円(税別)と、書面による譲渡手続きが必要です。
また、手続きの前に事務所への問い合わせも必要なので、ある程度の手間がかかります。
相続による譲渡も同じ条件です。
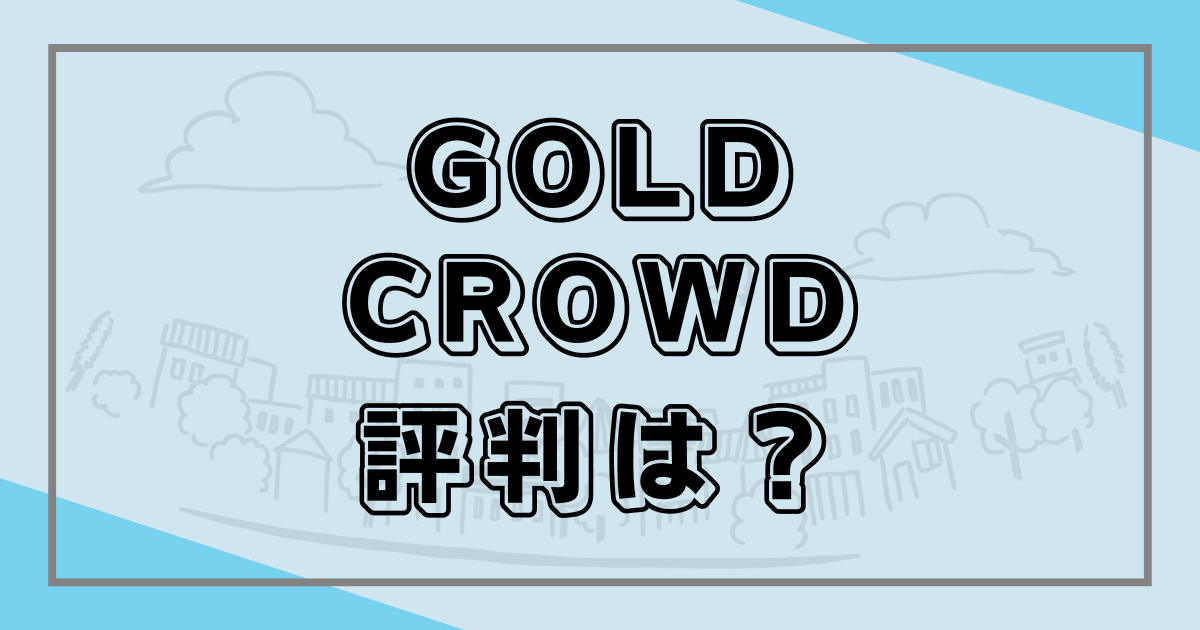
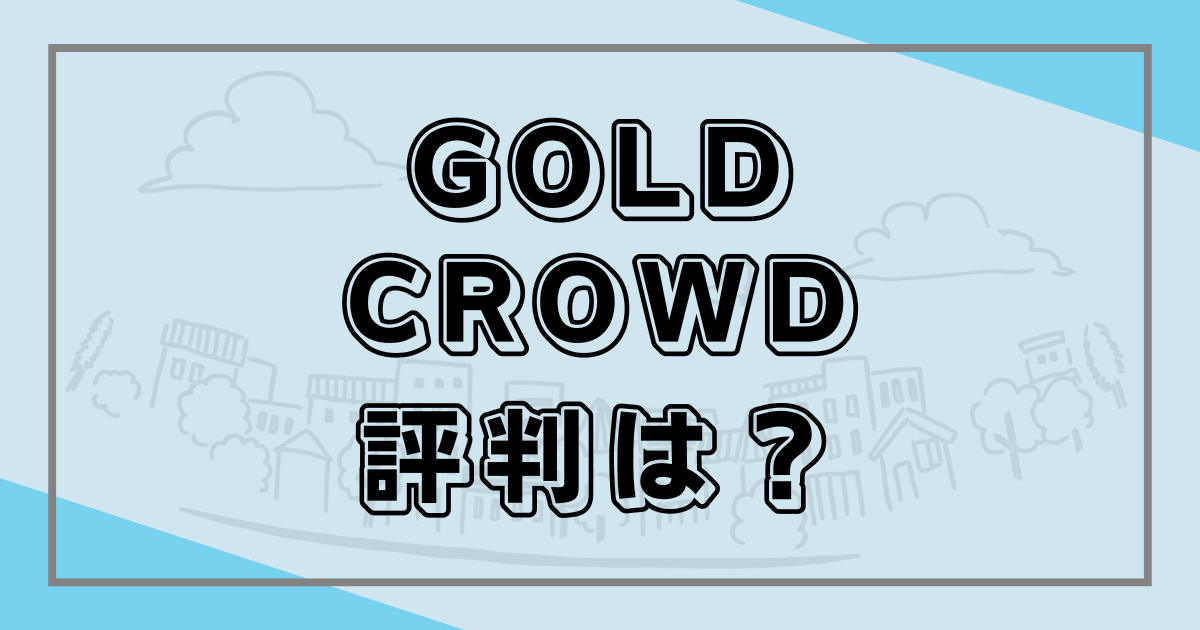
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング3. SOLS(SOLS Wallet)


SOLS(SOLS Wallet)とは、投資が出資した資金を元に、事業者が物件の運用・管理を行う不動産クラウドファンディングです。
SOLS(SOLS Wallet)の特徴は、資金を自由に出し入れできる点です。
「SOLS Wallet」の対象となっているファンドに投資すると、出資者が自分のタイミングで売却手数料なしで売却(払い戻し)ができます。
なお、GMOあおぞら銀行を利用すれば払い込み手数料も無料です。
SOLS Walletは、事業者が定期的に投資する不動産を入れ替えてくれるので、出資者は自分では何もすることなく、リスクを下げて投資ができます。
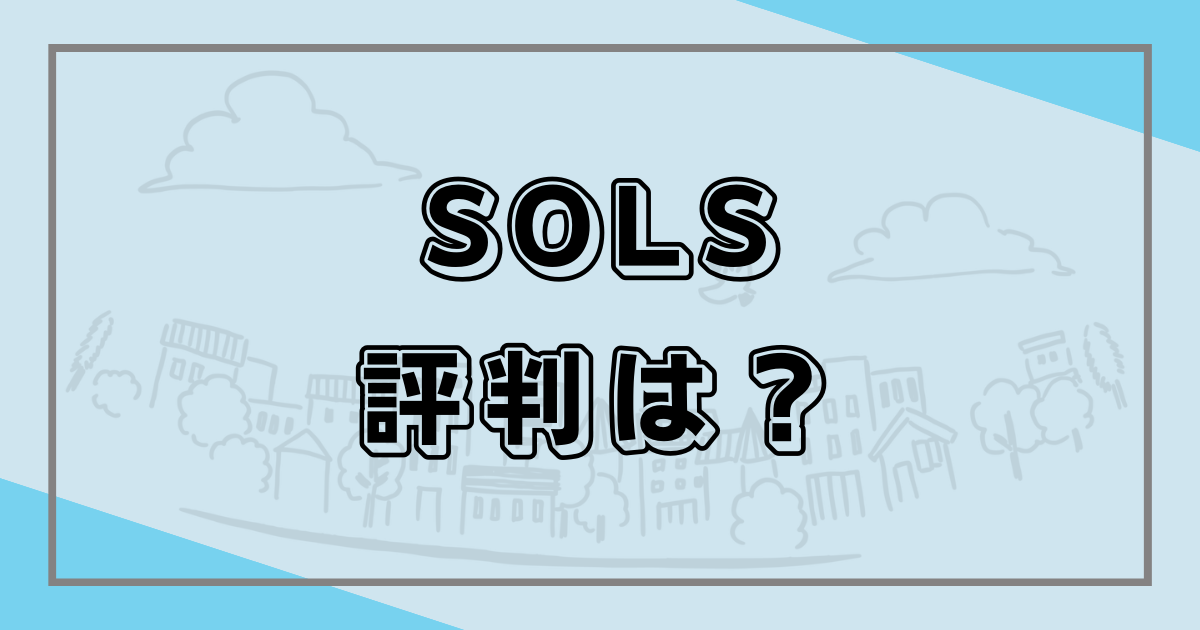
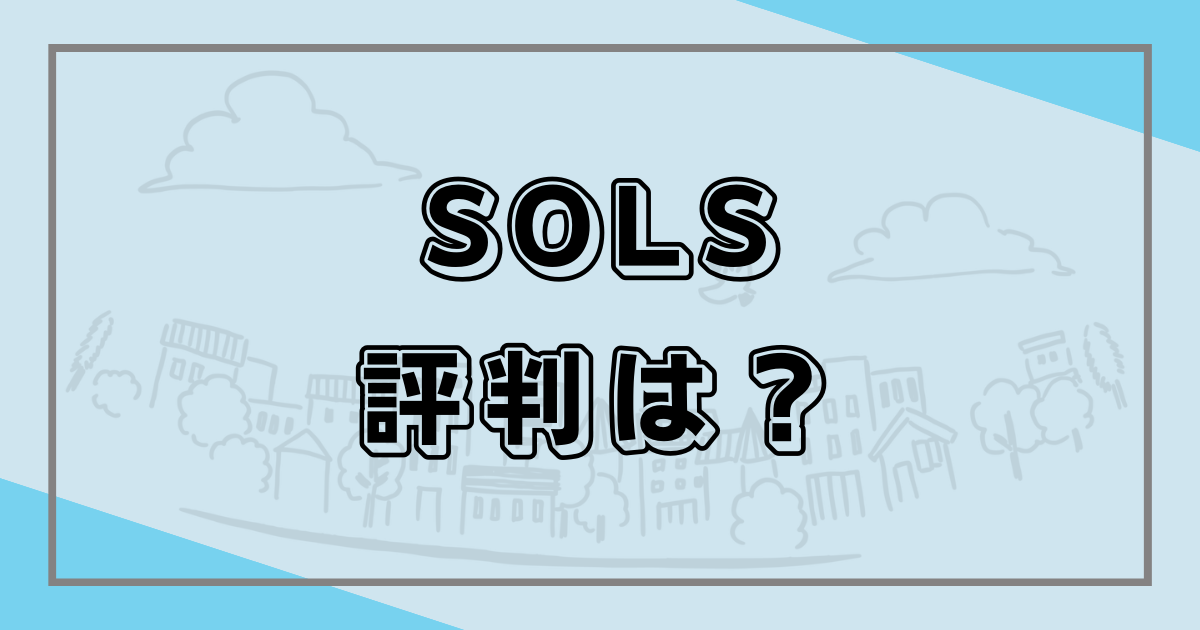
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング4. MyShopファンド


MyShopファンドは、専用の申込書で中途解約を申請すれば途中解約が可能です。
厳しい条件は定められていないので、比較的解約しやすいといえます。
譲渡も同じように専門の申請書が必要です。
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング5. ゴコウファンド


ゴコウファンドは、「譲渡」と「解約」で条件を分けている不動産クラウドファンディングです。
譲渡はどのファンドでも行えますが、解約はファンドによって条件が異なります。
譲渡の場合、1口500円の事務手数料と譲渡金額の3%の事務手数料がかかるので、注意しましょう。
なお、解約の場合は最低契約期間をすぎないと解約できないので、こちらも注意が必要です。
ちなみに、相続によって譲渡が必要になった場合は事務手数料が無料となっています。
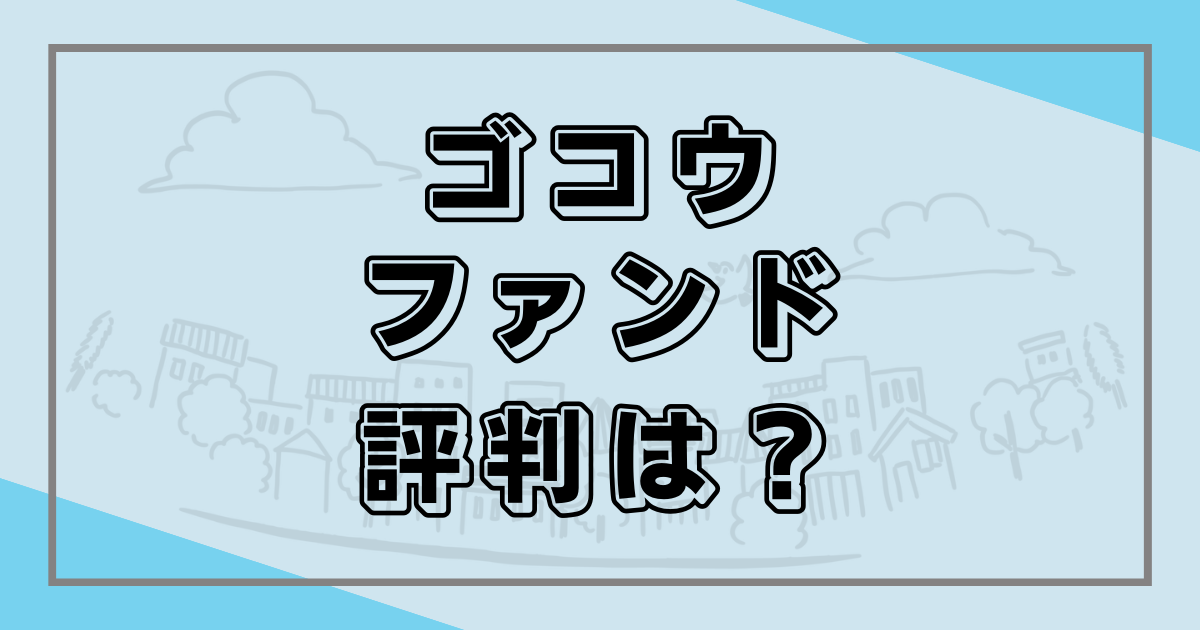
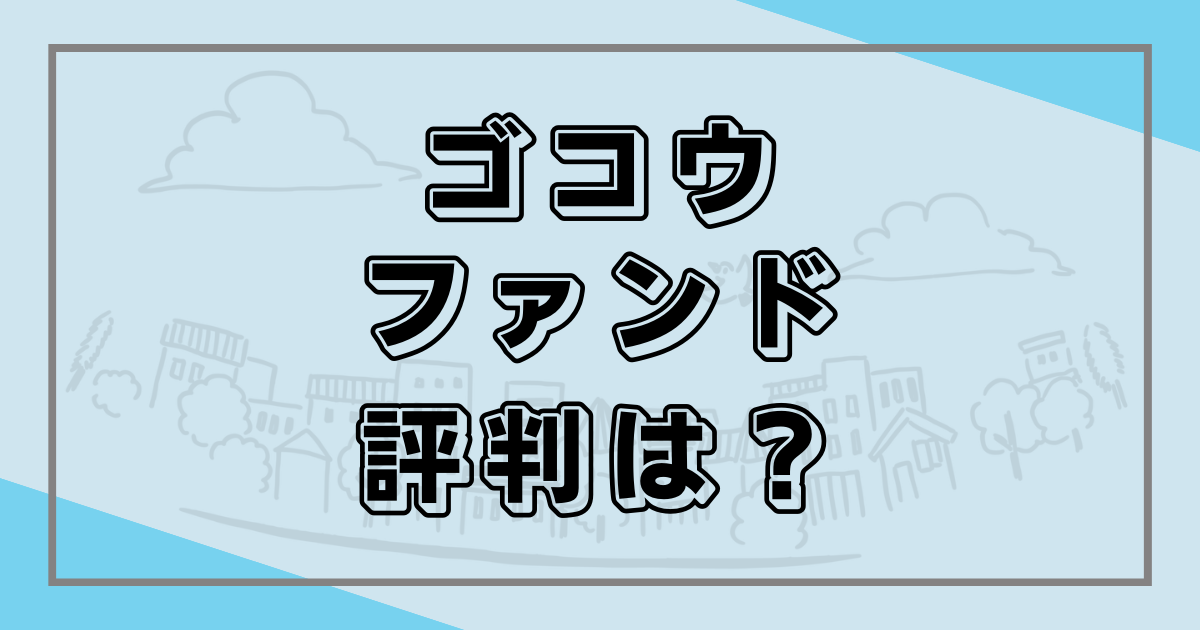
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング6. 汐留ファンディング


汐留ファンディングは、中途解約による出資金の現金化が可能です。
しかし、申請書をダウンロードし、事業者へ郵送しなければなりません。
インターネット上で手続きすることはできません。
また、解約までには30日ほどの日数もかかります。
さらに、1口あたり2,000円(税別)の解約手数料が発生しますので、解約を検討している場合は時間に余裕をもって申請しましょう。
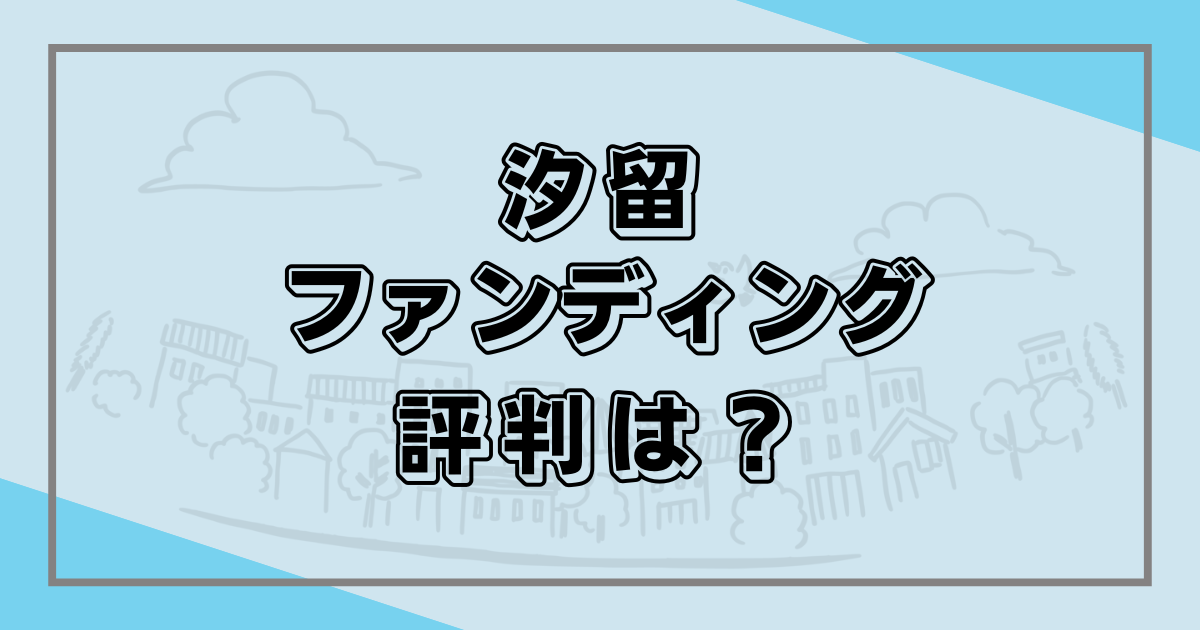
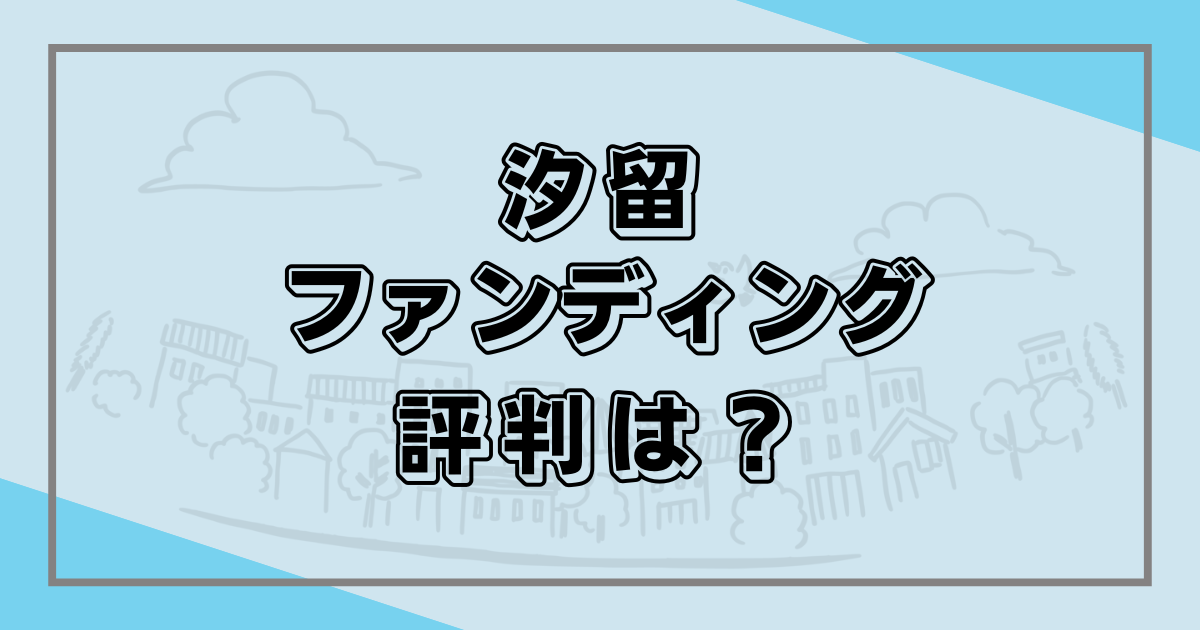
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング7. TSON FUNDING(ティーソンファンディング)


TSON FUNDINGでは、やむをえない事情がある場合だけ中途解約に応じてくれます。
どのような事例が「やむをえない事情」に該当するかは、契約成立前書面に記してあります。
わからないことがある場合は事務局にその都度問い合わせるのがおすすめです。
また、書面をダウンロードして必要事項を記入のうえ、郵送して許可を得る必要があります。
時間と手間がかかりますので、時間に余裕をもって申し込みましょう。
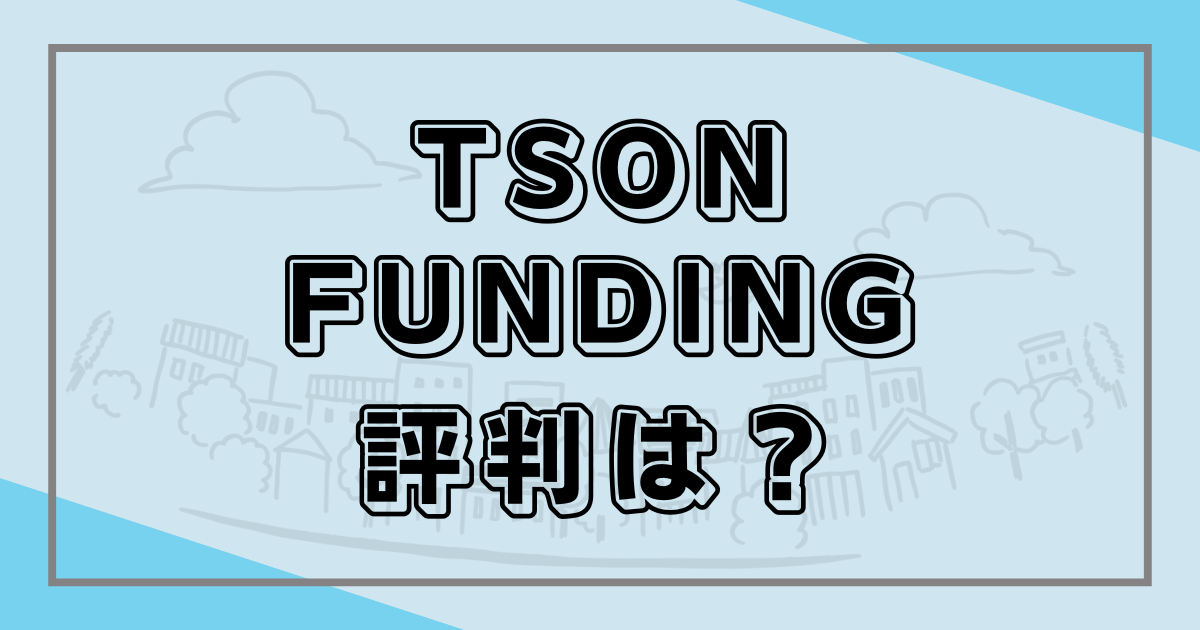
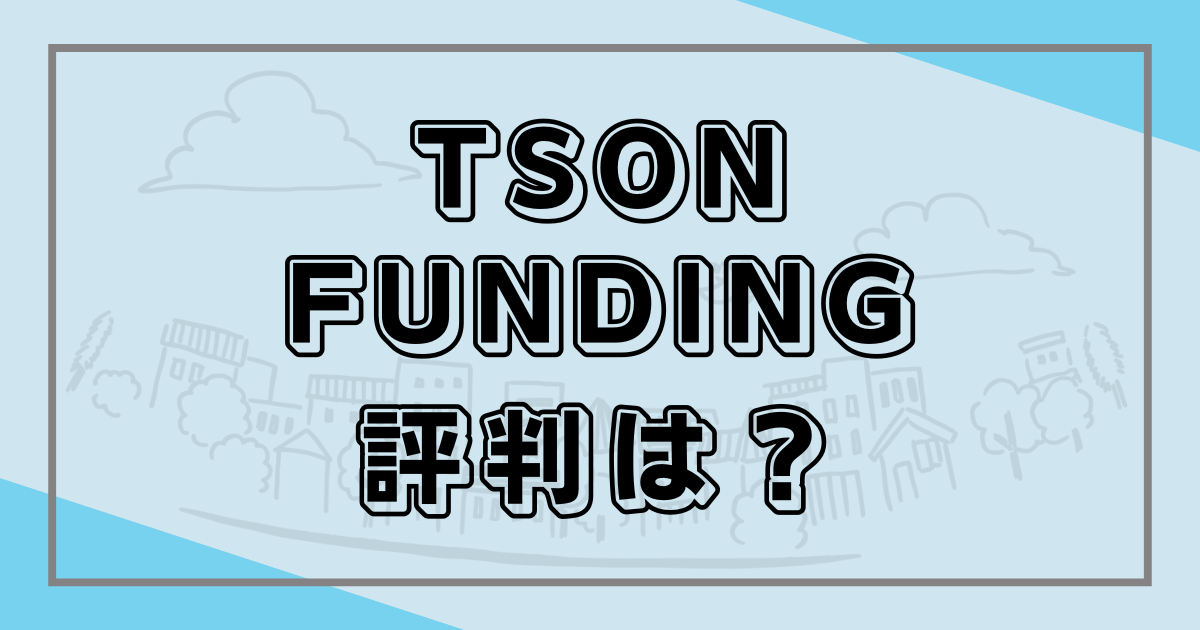
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング8. 大家どっとこむ


大家どっとこむは、2020年12月より1号案件の募集を開始し、2025年までに約100本を超えるファンドを取り扱ってきた、不動産クラウドファンディング投資の中では歴史があるサービスです。
大家どっとこむは、原則として途中解約はできないとしています。
しかし、案件ごとに持分買取制度を設けています。
持分買取制度は、買取手数料無料で大家どっとこむが買取をしてくれる制度で、買取時の公正な価格での買取となり、対象口数は申し込み金額の全額のみです。(振込手数料はかかる)
ただし、FunFunds案件は買取制度の対象外なので投資する際はその旨を理解しておきましょう。
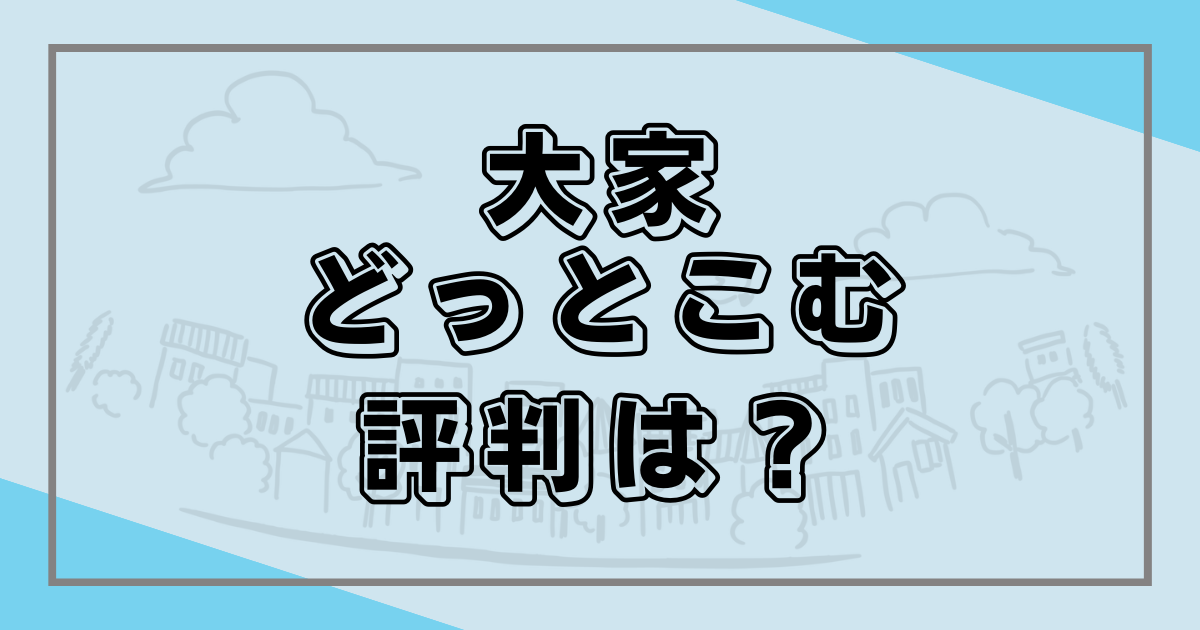
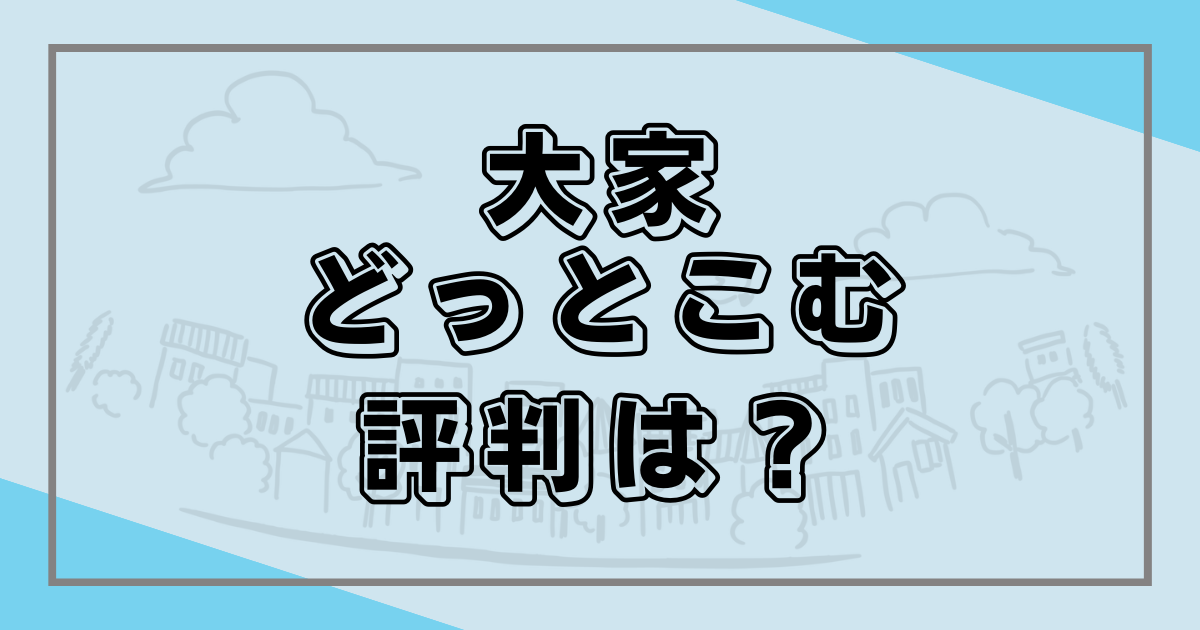
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディング9. ビギナーズクラウド


ビギナーズクラウドは、中途解約と譲渡、どちらも可能です。
専用の申込書で中途解約と出資金の払い戻しの申請が必要で、払い戻しには受理されてから30日程度の時間が必要です。
譲渡も同じ方法で行えます。
短期運用のファンドが多いのであまり使われる方はいないかもしれませんが、厳しい条件が定められていないので、比較的解約しやすいといえます。
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディングのメリット!
中途解約・譲渡できる不動産クラウドファンディングのメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 急に資金が必要になっても安心
- リスクを下げられる
- 相続がスムーズにいく
1つずつ説明していくので参考にしてください。
急に資金が必要になっても安心
まとまった資金を投資した場合、いざというときに解約できれば急に資金が必要になった時も対応できます。
特に、12ヶ月以上の運用期間が長いファンドに投資したい場合は、途中解約ができるシステムがあると安心です。
ただし、手数料等が発生するので注意も必要です。
リスクを下げられる
不動産クラウドファンディングは、元本保証がされていません。
運用期間中に「運用が危ない」「元本割れするかもしれない」といった情報を得る場合もあるでしょう。
そのような時に途中解約ができれば、元本割れリスクを下げられます。
特に、大きな金額を投資している場合は、途中解約をしたほうが手数料を差し引いても得な場合があるでしょう。
相続がスムーズにいく
出資者が運用期間中に亡くなり、相続が発生した場合は解約や譲渡ができたほうが便利です。
相続する際は、遺産の額がはっきりしていないと何かと不便が出てきます。
譲渡が行えれば、被相続人がスムーズに相続してそのまま投資が続けられます。
ファンドの中には、相続で譲渡する場合は事務手数料が無料なケースもあります。
高齢者が不動産クラウドファンディングを行う場合は、念のため譲渡ができるファンドを選ぶのがおすすめです。
まとめ
不動産クラウドファンディングは途中解約できるものとできないものがあります。
途中解約できればメリットがありますが、ファンドによっては解約までに時間がかかったり、手数料が高額だったりする場合もあるでしょう。
ファンドの中には数カ月で運用終了するものもあるので、途中解約するかもしれないといった場合は、短期運用のファンドに投資してみる方法もあります。
不動産クラファン「COZUCHI」が2,000円のアマギフプレゼント中!【ad】
人気不動産クラウドファンディングサービスである「COZUCHI」の特徴は以下のとおりです。
- 実質利回りの平均は10%超え
- 一度も元本割れがない
- 累計調達額1,000億円超えで業界No.1
そんなCOZUCHIが、当サイト限定で2,000分のアマギフをプレゼント中です!
公式サイトでもキャンペーンは実施していますが、キャンペーン金額が下がってしまうため、注意しましょう。



投資には投資家登録が必要なため、気になる方はお早めに無料の投資家登録をしてみてはいかがでしょうか。
本サイトのコンテンツは事業者の公式サイトから抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

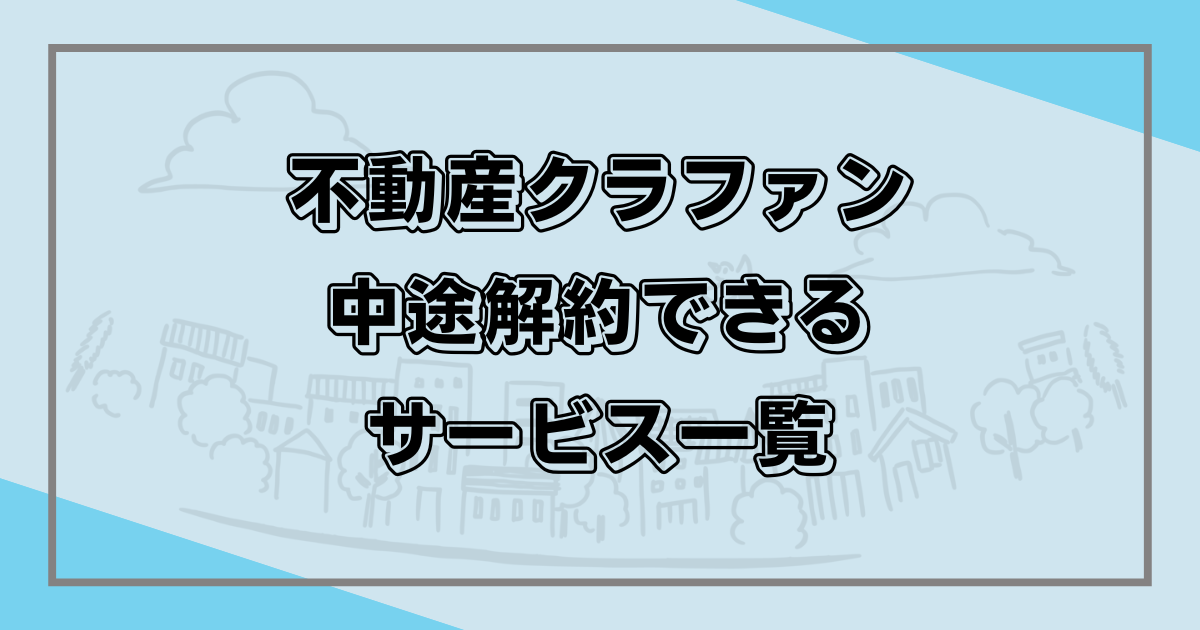




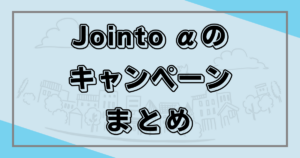
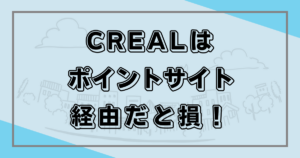
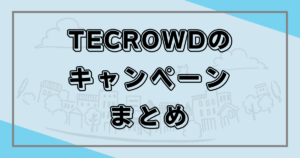
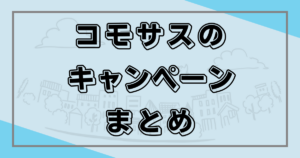
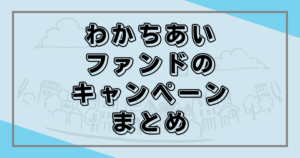
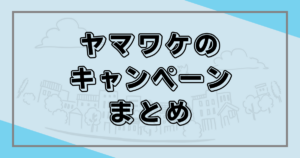
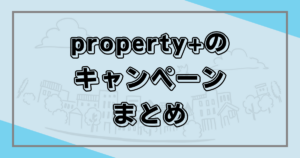
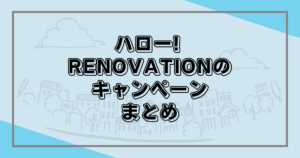
コメント