「不動産投資ファンドって何?」
「不動産投資ファンドのメリット・デメリットを知りたい」
不動産投資を検討している投資家の中には、不動産投資ファンドがどのようなものか知りたい、という方も多いのではないでしょうか。
不動産投資ファンドの仕組みや種類についてしっかりと理解してから利用したいですよね。
不動産投資ファンドについて詳しく紹介します。
☆CREALが当サイトと限定アマギフキャンペーン!☆
上場企業運営で、実績トップクラスの「CREAL」が注目を集めています。
そんなCREALが、当サイト限定タイアップキャンペーンを実施中です!
新規投資家登録だけで、Amazonギフト券2,000円分、投資額に応じて最大48,000円分のAmazonギフト券がもらえます。
公式サイトではキャンペーンは実施していないため、注意してくださいね。
豪華なキャンペーンが実施されているこの機会に無料の投資家登録をしてみてはいかがでしょうか。
不動産投資ファンドとは?仕組みを解説!
不動産投資ファンドは、複数の投資家から集めた出資金をもとにして、不動産の運用で得られた収益を投資家に分配する仕組みです。
複数の投資家が共同で出資するため、個人での投資が難しい商業ビルやオフィスビルなどの高額不動産への投資も可能になります。
不動産投資ファンドで得られる収益には、家賃収入のインカムゲインと売却益のキャピタルゲインの2種類があります。
不動産投資ファンドは2種類
不動産投資ファンドは、以下の2種類に分類されます。
- 不動産投資信託(REIT)
- 不動産特定共同事業
それぞれの特徴を解説します。
不動産投資信託(REIT)
不動産投資信託は、以下の2つに分類されます。
- 公募ファンド(J-REIT)
- 私募ファンド
以下では、違いを解説します。
公募ファンド(J-REIT)
公募ファンドとは、不特定多数の投資家から資金を調達するファンドです。
公募ファンドは証券取引所に上場しているため、証券会社や銀行を介して広く販売されているのが特徴です。
株式と同様に価格変動があり、証券取引所でのリアルタイム取引ができます。
そのため、買いたいときに買って売りたいときに売れる流動性の高い金融商品です。
アメリカで生まれた仕組みであるREITにJAPANの頭文字をつけてJ-REITと呼ばれています。
J-REITは5~10万円程度から投資できます。
銘柄によって異なりますが、J-REITの利回りは3~5%程度です。
私募ファンド
私募ファンドは、証券取引所に上場していないため、市場での取引はできません。
事業法人や機関投資家など、特定の投資家を対象にしているファンドです。
出資額が数千万円~数億円単位のファンドが中心です。
不動産特定共同事業
不動産特定共同事業とは、不動産特定共同事業法に基づき運営されている投資商品です。
不動産小口化商品とも呼ばれています。
不動産特定共同事業法とは、不動産ファンドを運営している事業者を対象に適用される法律です。
業務適正運営に関する仕組みと投資家利益の保護を目的として制定されました。
不動産特定共同事業は、以下の3つに分類されます。
- 任意組合型
- 匿名組合型
- 賃貸型
任意組合型
任意組合型では、投資家と事業者が任意組合契約を締結します。
任意組合契約とは、複数の投資家の出資により、共同で事業を運営することを目的とした契約です。
任意組合型では、1つの不動産を複数の投資家と共同で所有するため、比較的少額でも不動産の一部の所有権を得られる点が特徴。
任意組合型の分配金は不動産所得として課税されます。
そのため、相続や贈与の節税対策ができる有効な手段のひとつとして活用されています。
匿名組合型
匿名型では、投資家と事業者で匿名組合契約を締結し、投資家は組合に対して出資します。
匿名組合型では不動産の所有者は事業者のため、投資家は不動産の所有権を得られません。
1口1万円程度の少額から始められるものが多い不動産クラウドファンディングは、ほとんどが匿名組合型です。
匿名組合型の分配金は、雑所得として総合課税の対象になります。
賃貸型
賃貸型では、複数の投資家の共同出資で購入した不動産の管理・運用を不動産特定共同事業者に委託します。
投資家と事業者が賃貸借契約を締結し、運用がおこなわれます。
賃貸型では、複数の投資家が共同で不動産を所有しているため、所有権を有するのは投資家です。
賃貸型の分配金は、不動産所得に分類されます。
不動産投資ファンドの強み・メリット2選
不動産投資ファンドの強みとメリットは、以下の2つです。
- 少額から始められる
- 分散投資しやすい
それぞれ解説します。
少額から始められる
不動産投資ファンドでは、少額から不動産投資を始められます。
利用するサービスによって最低投資金額は異なりますが、1口1万円から投資できるサービスもあります。
不動産投資の初心者でも気軽に始めやすいでしょう。
分散投資しやすい
不動産投資ファンドは少額でできるため、分散投資しやすい特徴があります。
不動産投資には、空室リスクや災害リスク、家賃下落リスクなど、特有のリスクが複数あります。
複数の不動産へ分散して投資することで、特定の不動産の影響を受けにくくなるため、リスクを軽減できるでしょう。
不動産投資ファンドの注意点・デメリット2選
不動産投資ファンドの注意点とデメリットは、以下の2つです。
- 短期間での大きなリターンは期待できない
- レバレッジ効果が得られない
それぞれ解説します。
短期間で大きなリターンは期待できない
不動産投資ファンドでは投資金額が少額のため、短期間で大きなリターンは期待できません。
株式投資のように短期間で大きなリターンは得られませんが、長期的な目線でコツコツ利益を積み上げたい投資家には向いている投資方法です。
レバレッジ効果が得られない
不動産投資ファンドへの投資に不動産投資ローンを活用することはできません。
そのため、借入金を活用したレバレッジ効果が得られないデメリットがあります。
レバレッジ効果とは、「テコの原理」のように小さな力で大きな効果を得る仕組みです。
不動産投資におけるレバレッジ効果とは、他人資本である借入金を活用して投資効率を上げることで、自己資本に対する収益性を最大限に高めることを指します。
不動産投資ファンドでは、用意できる自己資金の範囲内での投資になるため、不動産投資ローンを組む必要はありません。
不動産投資ローンに抵抗がある方やまとまった資金が用意できない方にとっては、不動産投資を始めるハードルが低くなるでしょう。
不動産投資ファンドのリスク
不動産投資ファンドには、元本割れリスクがあります。
一般的な不動産投資ファンドでは、元本が保証されていません。
そのため、不動産の運用によっては、元本割れや損失を被る可能性があるため、注意が必要です。
不動産投資ファンドを利用する際には、元本割れリスクについてしっかり理解してから始めましょう。
また、匿名組合型の不動産クラウドファンディングでは、元本割れリスクを軽減できる優先劣後システムを導入しているサービスが多くあります。
優先劣後システムとは、優先出資者である投資家が利益を優先して得られる一方で、損失分は劣後出資者である事業者が先に補填します。
事業者が出資する割合である劣後出資割合の範囲内で、投資家の元本が守られる仕組みです。
一般的な不動産クラウドファンディングの劣後出資割合は、10~30%程度。
劣後出資割合までの損失がカバーできるため、元本の安全性が高まります。
不動産投資ファンド会社のランキング一覧
不動産投資ファンド会社を時価総額順に紹介します。
時価総額とは、株価×発行済み株式数で求められる企業の規模を示す指標です。
時価総額が高いほど市場においての信頼度も高まるため、倒産リスクが低くなる傾向があります。
不動産投資ファンド会社のランキング一覧は、以下の通りです。(2025年2月21日時点)
| 不動産投資ファンド会社 | 時価総額(百万円) |
| 日本ビルファンド投資法人 | 1,052,913 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 774,749 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 671,089 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 664,430 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 650,108 |
| KDX不動産投資法人 | 610,672 |
| GLP投資法人 | 605,849 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 556,365 |
参考:不動産投資信託業界 : 銘柄一覧 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版
不動産投資ファンドと現物不動産投資の違い
不動産投資ファンドと現物不動産投資には、以下の違いがあります。
| 不動産投資ファンド | 現物不動産投資 |
|
・複数の投資家から資金を調達 ・少額からでも始められる ・専門知識は不要 ・匿名組合型では所有権が得られない ・任意組合型、賃貸型では不動産の一部の所有権が得られる ・商業施設やオフィスビル、ホテルなどの高額不動産への投資も可能 ・不動産投資ローンは利用できない |
・多額の自己資金を用意する ・頭金、登記費用、仲介手数料、税金などの諸費用が必要 ・管理委託費や固定資産税などのランニングコストがかかる ・専門知識が必要 ・不動産の所有権を得られる ・アパートやマンションなどの居住用住宅を購入する ・不動産投資ローンを利用できる |
多額な資金が必要になる現物不動産投資と比較すると、不動産投資ファンドは少額から始められるのが大きな魅力です。
複数の投資家から資金を調達する仕組みのため、個人での購入が難しい高額不動産への投資が可能です。
不動産投資ファンドでは、種類によって不動産の所有権の有無が異なります。
主要の不動産投資ファンド2選を紹介
ここでは、数ある不動産投資ファンドの中でも、より高利回りに特化しているサービスと堅実にリターンを狙えるサービスの2社を紹介します。
安全性&高利回りにこだわりたい方向けサービス「レベチー」


不動産クラウドファンディングでは珍しい不動産特定共同事業3号・4号事業の許可を受けているのが、「LEVECHY(レベチー)」です。
レベチーはこの3号4号事業により、信託保全が必須、倒産隔離もでき安全性が高められています。
※信託保全:未投資金を運営会社の口座ではなく信託銀行の口座で信託管理。運営会社が倒産しても未投資金が差し押さえの対象とはならない。
※倒産隔離:ファンドごとにSPCという別会社を作り、そこで不動産を保有・運用する。運営会社が倒産しても対象不動産は差し押さえの対象にならない。
また、ローンを利用することにより、高利回りファンドを組成していることも特徴です。
これまでに募集されたファンドの利回りは7.9%と高めです。(2025年3月時点)
レベチーと当サイト限定タイアップキャンペーン実施中!
レベチーでは、当サイトからの登録経由での新規投資家登録で1,000円分のAmazonギフト券が1,000円分もらえるキャンペーンを実施中です!
| 内容 | 当サイトのリンク経由で新規投資家登録をするとAmazonギフト券1,000円分プレゼント |
| 期間 | 記載無し |
| 条件 | 当サイトのリンク経由で新規投資家登録をする |
| 注意点 | ・公式サイトからは対象外 ・キャンペーンは急に終了する可能性がある ・リンク遷移先にキャンペーンの記載はない ・配布は登録月の翌月中 |
レベチーについての口コミやメリットデメリットなどを知りたい人は、下記の解説記事も参考にしてください。
堅実に一定のリターンを積み上げたい人向けのサービス「CREAL(クリアル)」


CREALは東証グロース市場に上場しているクリアル株式会社が運営しているサービスです。
過去のファンドの募集額、募集件数共に業界トップクラスの実績を誇ります。
平均利回りは4〜5%と、不動産クラウドファンディングの中でも一般的な利回りですが、マスターリース契約(空室保証)を結んでいる案件もあるため、リスクを抑えた投資が可能となっています。
配当も定期的に分配されるので、定期的な収入を得たい方にもおすすめです。
しかし、CREALが募集するファンドは2年程度の運用期間のものが多く、他のサービスより長い傾向があります。
長期的にほったらかし投資をしたい方には向いていますが、資金ロックの期間を短くしたい方は他のサービスも検討するといいでしょう。
CREALはアマギフがもらえるキャンペーンを実施中
2025年3月現在、CREALでは投資家登録と初回投資でAmazonギフト券が最大50,000円分もらえるキャンペーンを実施中です。
キャンペーンの簡単な詳細は以下の通りです。
| 内容 |
①新規投資家登録で2,000円分のAmazonギフト券プレゼント |
| 期間 | 記載無し |
| 条件 | ①無料の投資家登録をする ②会員登録から60日以内に50万円以上投資する |
| 注意点 | ・公式サイトからは対象外 ・投資家登録は会員登録から60日以内に完了させる必要がある |
新規投資家登録だけでも2,000円分のAmazonギフト券がもらえる豪華なキャンペーンです。
この機会に無料の会員登録をしてみてはいかがでしょうか。
CREALについての口コミやメリットデメリットなどを知りたい人は、下記の解説記事も参考にしてください。
まとめ
今回紹介した不動産投資ファンドについて、重要なポイントを4つにまとめました。
- 不動産投資ファンドは投資家からの出資を受け不動産を運用して得られた収益を投資家に分配する仕組み
- 不動産投資信託(REIT)と不動産特定共同事業の2種類
- 少額から始められる
- 分散投資しやすい
比較的少額からでも始められる不動産投資に興味がある方は、不動産投資ファンドの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
不動産クラファン「COZUCHI」が2,000円のアマギフプレゼント中!【ad】
人気不動産クラウドファンディングサービスである「COZUCHI」の特徴は以下のとおりです。
- 実質利回りの平均は10%超え
- 一度も元本割れがない
- 累計調達額1,000億円超えで業界No.1
そんなCOZUCHIが、当サイト限定で2,000分のアマギフをプレゼント中です!
公式サイトでもキャンペーンは実施していますが、キャンペーン金額が下がってしまうため、注意しましょう。



投資には投資家登録が必要なため、気になる方はお早めに無料の投資家登録をしてみてはいかがでしょうか。
本サイトのコンテンツは事業者の公式サイトから抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。

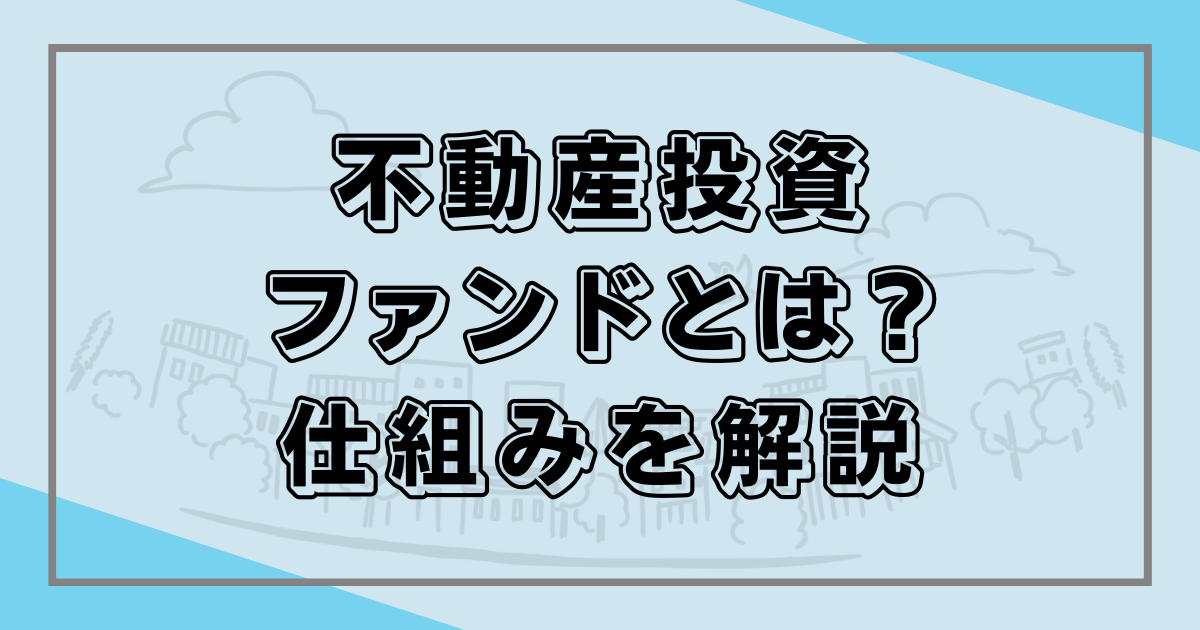




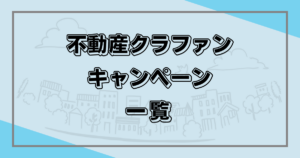
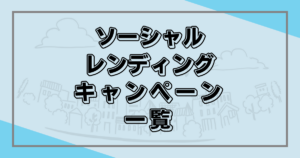
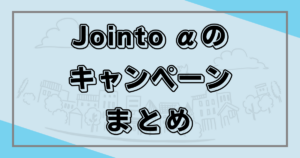
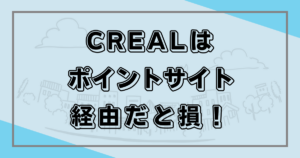
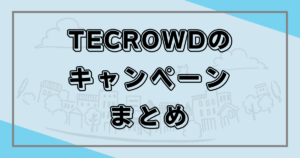
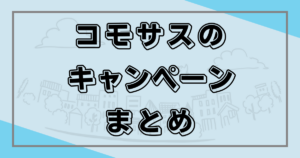
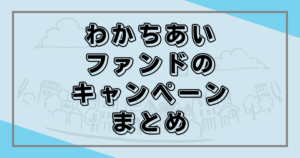
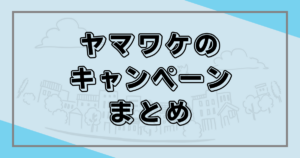
コメント