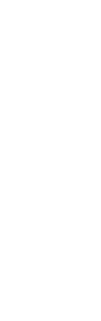50代を迎えて感じる「家はこのままでいいの?」という悩み。ライフステージの変化にあわせた住まいとは
 50代を迎えると、30歳前後で購入したマンションや建てた家が20年経ち、子供が自立して部屋があまっていたり、家が古くなって修繕費が必要になってきたりと、マイホームについて悩む方が多くいます。鈴木マコトさん(仮称)、ユウコさん(仮称)ご夫婦も、同様です。子供2人が就職、進学でそれぞれ家を離れ、部屋が余っている状態に。子供たちの部屋はどうしよう?書斎をつくる?いっそ住み替える?など、いろんな考えが浮かんでは、決め切れずにいます。まずは50代の持ち家世帯に、どんな選択肢があるのか整理してみましょう。
50代を迎えると、30歳前後で購入したマンションや建てた家が20年経ち、子供が自立して部屋があまっていたり、家が古くなって修繕費が必要になってきたりと、マイホームについて悩む方が多くいます。鈴木マコトさん(仮称)、ユウコさん(仮称)ご夫婦も、同様です。子供2人が就職、進学でそれぞれ家を離れ、部屋が余っている状態に。子供たちの部屋はどうしよう?書斎をつくる?いっそ住み替える?など、いろんな考えが浮かんでは、決め切れずにいます。まずは50代の持ち家世帯に、どんな選択肢があるのか整理してみましょう。
目次
持ち家率が高い50代に訪れる変化
子供の自立で家の広さが気になり始める
鈴木家のように、子供が自立して家を出ると、子供部屋が空き部屋になります。一度家を出たら、帰省したときに泊まる部屋や寝具は必要でも、その先また一緒に暮らす可能性は低いでしょう。そうなると、部屋数の多さ、リビングの広さを持て余すことに。年齢を重ねると掃除や管理が大変になり、維持費や固定資産税などに見合っているのか?という疑問を感じるでしょう。部屋があまっている、家が広すぎると感じたら、残された家族の生活に合った間取りを考える時期がきているのかもしれません。
仕事やライフスタイルの変化
子供の自立以外にも、ライフスタイルの変化が訪れることがあります。例えば、転職やリモートワークの普及で、通勤距離の優先度が変わる、夫婦のどちらかが退職して家にいる時間が増える、などです。時間に余裕がうまれると趣味を追求するようになり、趣味や生活スタイルに合わせた住環境を求めるようになることも考えられます。
親の介護や健康面の変化
 50代の親世代は、後期高齢者の75歳以上が多いのではないでしょうか。鈴木家の親は80代。とくにマコトさんの父はひとり暮らしで、この先どうすべきか思案中です。だんだんと車の運転や火の始末にも不安がよぎるようになり、離れて暮らす親はこの先どうやって暮らしていくのか、親が住んでいる家はどうするのかと悩んでいます。引き取って一緒に暮らすなら、住宅のバリアフリー化、親の住まいの売却もすることになり、考えることが山積みです。
50代の親世代は、後期高齢者の75歳以上が多いのではないでしょうか。鈴木家の親は80代。とくにマコトさんの父はひとり暮らしで、この先どうすべきか思案中です。だんだんと車の運転や火の始末にも不安がよぎるようになり、離れて暮らす親はこの先どうやって暮らしていくのか、親が住んでいる家はどうするのかと悩んでいます。引き取って一緒に暮らすなら、住宅のバリアフリー化、親の住まいの売却もすることになり、考えることが山積みです。
どの選択肢が最適か?考えるべきポイント
当然ながら人によって状況が異なるため、最適な選択肢も異なります。自分にとってはどの選択肢が最適なのか考えるとき、まずはこんなポイントをみていきましょう。
今後のライフプランと住まいのバランス
残業が減って家にいる時間が長くなるなら、ゆったりと寛げるスペースや趣味のものを置く場所が欲しくなるかもしれません。鈴木家の場合、マコトさんは出張が減って在宅時間が増加。ユウコさんは子供の手が離れて自由時間が増えたことで、友人と会ったり地域ボランティアを始めたりと、外に出る機会が増えました。そうなると、マコトさんは自分だけの空間が欲しい、ユウコさんは家事が楽になる生活が理想です。まずは、今後どうしていきたいかを考えてみてください。
経済的な負担や資産価値の維持
今後どうしていきたいかを考えるうえで、収入や大きな支出の予定は大事なポイントです。マコトさんは50歳、職場では最近75歳まで勤務を延長できるようになり、まだ20年は働いて収入も得たいと考えています。多くのご家庭では、子どもの大学進学で一時的に収入と支出のバランスがマイナスに近くなるものです。鈴木家は子供2人のうち1人は就職して大学の費用や仕送りが必要なくなったため、収支バランスは改善。まだ在学中の子供もいて今すぐ家にお金をかけることは難しいものの、順調にいけば3年ほどで落ち着く予定です。持ち家の資産価値を維持するために、大きな費用をかけなくても、家の点検や補修、部分的なリフォームを考えるのもひとつの手です。点検や補修などの記録はしっかりと保管しておくことで、売却するときに適切な維持管理をしている大事な資料となります。
「売る」「住み替える」「リフォーム」のメリット・デメリット
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 家を売る |
|
|
| 住み替える |
|
|
| リフォーム |
|
|
50代のライフステージの変化に合わせて、住まいの選択肢を整理
50代はまだまだ現役世代で住まいの幅広い選択肢があるものの、仕事や親のことなど、すぐには決められないことも多いでしょう。鈴木家も、いまは子供2人とも自立して部屋が余っていますが、じつは上の子が就職するときに戻ってくる可能性もありました。まだ下の子は大学生で、この先戻ってきたり、二世帯住宅にする可能性もゼロではありません。マコトさんの父親に「一緒に暮らそう」と提案もしましたが、慣れ親しんだ家や地域で暮らしたいと、話し合いは進まないままです。悩んでいるうちは大きな決断を避けて、どういう状態になったら決めるなど、まずは今後の方針を決めることに留めるといいのかもしれません。
今後のライフスタイルをよく考えて、マイホームをどうしていくべきか決めていきましょう!
執筆:ライター Y